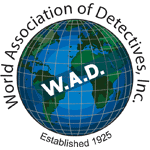学歴詐称は、採用企業にとって重大なリスクとなる問題です。採用候補者が虚偽の学歴情報を提供し、自身の学歴を水増しする行為は、採用プロセスの公正性と信頼性に対する脅威となります。
本記事では、学歴詐称の犯罪性について解説し、さらに事前に学歴詐称を見抜くための有効な調査方法や、発覚時の適切な対処法について詳しくご紹介します。採用企業が学歴詐称を未然に防ぐために必要な知識やポイントをお伝えします。
学歴詐称とは?
学歴詐称とは、個人が自身の学歴について履歴書や職務経歴書、求人応募書類などで虚偽の学歴情報をを提供したり、偽造した卒業証明書や学位を使用したりする行為のことを指します。つまり、本来の学歴や学位とは異なる情報を意図的に伝え、他人を欺く行為です。
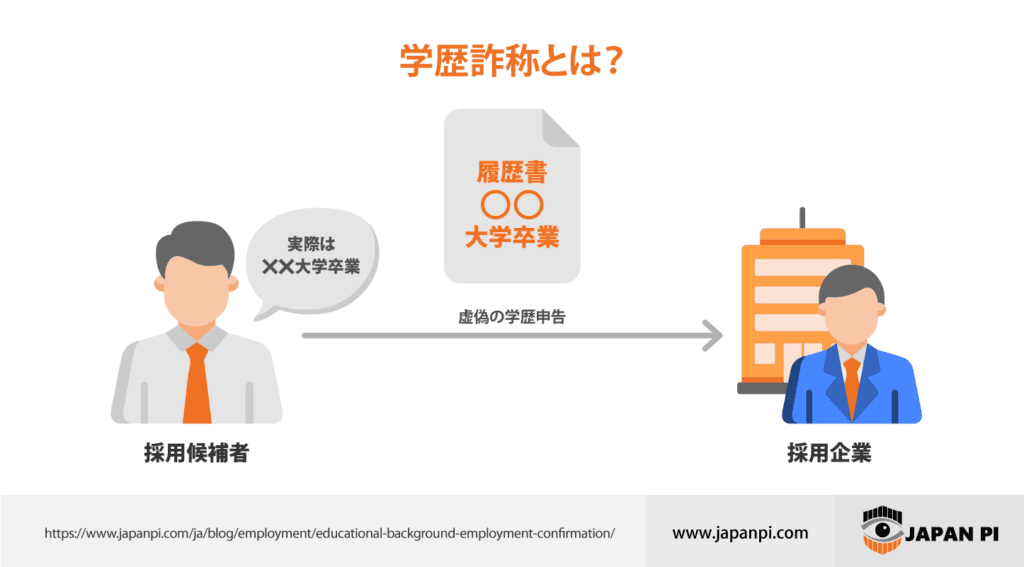
学歴詐称は犯罪?犯罪になるケースとは
学歴詐称が犯罪となるかどうかは、程度の差や文書偽造があったかどうかによって異なります。一般的には、以下のようなケースで学歴詐称は犯罪と見なされることがあります。
1. 偽造した卒業証明書や学位を使用して詐欺行為を行った場合
もし、偽造した卒業証明書や学位を使用して就職や進学、公的な手続きなどを行い、他人を欺いた場合は、詐欺罪や偽造文書行使罪などの犯罪として処罰される可能性があります。
2. 学歴詐称によって経済的な利益を得た場合
学歴詐称によって就職や昇進、報酬の増加など経済的な利益を得た場合、詐欺罪や不正競争防止法違反などの犯罪とみなされ、法的な責任を問われることがあります。
3. 学歴詐称によって公的な地位や権限を悪用した場合
学歴詐称を利用して公的な地位や権限を獲得し、それを悪用する行為は、背任罪や公務員職権濫用罪などの犯罪として処罰される可能性があります。
学歴確認 | 学歴詐称を事前に見抜くための方法
学歴確認は、採用企業が候補者の提出した学歴情報の正確性を確認するために行う重要なプロセスであり、重要な採用調査の手段の一つです。日本の大学のほとんどでは、本人に卒業証明書を発行して学歴記録を証明する手法を取っています。通常、その学校が指定する専用の申請用紙や委任状を使って、卒用証明書を取得することになります。
学歴詐称を事前に見抜くためには、以下の方法があります。
卒業証明書の提出依頼
求職者や進学者に対して、卒業証明書の提出を求めることが一般的です。ただし、卒業証明書が偽造さあれる提出された証明書を元に、卒業校にその証明書が変造されていないかどうかを確認する方法です。
この場合、本人から以下の書類を提出してもらいましょう。
- 卒業証明書
- 身分証のコピー
- 調査担当者への委任状(調査委任状見本)
卒業校での真偽確認
卒業証明書の提出だけでなく、卒業校の教務課に、電子メールでそれらの書類を添付して送ります。通常、この方法で、卒業校から提出した証明書の真偽についての回答が得られます。
卒業証明書や身分証の偽造代行業者は、ネット検索で簡単に見つかります。卒業証明書の偽造専門業者が逮捕された事例もあります。確認せずに、本人の提出書類を信じることはできません。

卒業証明書の代理取得
求職者や進学者が自身の卒業証明書を取得できない場合、法的な手続きを経て卒業証明書の代理取得を行うことがあります。この場合、調査担当者が卒業証明書を代理取得できるよう、本人に委任状を書いてもらいます。通常、各学校のウエブサイトで、証明書取得用の申請書や委任状をダウンロードして、本人にその記載と手続きを依頼することになります。
そして、本人が卒業証明書卒業校に依頼する時に、捜索調査担当者の住所にしてもらいます。この方法なら、卒業後から調査担当者に直接証明書が届きますので、内容が書き換えられる余地はありません。
例えば、東京大学(The University of Tokyo)の卒業証明書や成績証明書の確認でしたら、このページに申請方法の説明があります。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/alum-services/f03.html
メディアサーチでの学歴確認
在学中の部活動オンライン記事や、ソーシャルメディア、過去の新聞記事などで、採用候補者の名前がヒットする場合があります。本人の自己申告記事以外の客観的な記事で、在籍が確認取れれば、それで在学があったと認定してもいいかもしれません。
大学院卒業者の卒業確認
大学院卒業者であれば、修士論文や博士論文が、国立国会図書館の文章リストに収録されている可能性が高いです。大学院卒業者の場合は、ほとんどの場合、国立国会図書館のデータベースで卒業確認が可能です。
同窓会名簿での学歴確認
同窓会の名簿や交流サイトなどを活用して、他の卒業生との情報交換を行うことも有効です。2005年の個人情報保護法施行以前は、日本国内のほとんどの高校や大学の同窓会名簿が名簿業者に流通していました。
今も、ERA(イアラ)などの、名簿業者に、2005年以前に流通していた同窓会名簿のストックがあります。2005年以降卒業の年齢の人物であれば、過去の同窓会名簿で、卒業確認が可能です。
これらの方法を組み合わせて学歴詐称を事前に見抜くことが重要です。適切な調査と確認を行うことで、信頼性の高い学歴情報を得ることができます。
学歴詐称が発覚・バレた場合の対処法
学歴詐称が企業内で発覚した場合、以下のような対処法があります。
内部調査の実施
学歴詐称の疑いが浮上した場合、企業は内部調査を実施します。関係者や関係部署との面談や文書の確認など、徹底的な調査を行うことで真相を明らかにします。
関係先への照会
対象者に卒業したとされる教育機関からの卒業証明書の提出を求めたり、その証明書の真偽の確認を行います。
法的な措置の検討
学歴詐称が刑事的な要素を含んでいる場合、企業は法的な措置を検討します。法的な専門家や弁護士の助言を受けながら、適切な法的手続きを進めます。
内外への報告
学歴詐称が発覚した場合、企業は内部関係者や関係機関、関係企業に対してその事実を報告する必要が生じる場合があります。内部では、学歴詐称の不正社員が優遇される不公平な状況を作らないことが重要です。当該人物が学歴詐称によって、関係先にも不利益をもたらした場合は、すみやかに事実報告をする必要があります。
公表や情報の共有
学歴詐称の事実を公表し、他の企業や関係者との情報共有を行うことが重要です。業界内での警戒や注意喚起を促すことで、学歴詐称の被害を最小限に抑えることができます。
雇用や契約の見直し
学歴詐称が明るみに出た場合、関与した個人の雇用や契約を見直す必要があります。詐欺行為によって得た地位や特典は失われ、適切な措置が取られることもあります。
まとめ
学歴詐称は採用企業にとって深刻なリスクであり、採用プロセスの公正性と信頼性に対する脅威となります。この記事では、学歴詐称の犯罪性について解説し、事前に詐欺を見抜く方法や発覚時の対処法について詳しく紹介しました。
学歴詐称が犯罪に該当するかどうかは国や地域の法律によって異なりますが、偽造した卒業証明書や学位を使用したり、経済的な利益を得たり、公的な地位や権限を悪用したりする場合には犯罪とみなされることがあります。
採用企業は学歴詐称を未然に防ぐために、効果的な調査方法を使用する必要があります。卒業証明書の提出依頼や卒業校での真偽確認、メディアサーチや同窓会名簿を活用した学歴確認などの手法が有効です。
また、学歴詐称が発覚した場合の適切な対処法として、内部調査の実施、関係者への聞き取り、法的な措置の検討、内外への報告、情報の公表や共有が重要です。これにより、詐欺行為に関与した個人や関連組織に対して適切な措置が取られる可能性が高まります。
学歴詐称の防止と対処は、採用プロセスの信頼性と企業の評判を守るために欠かせない重要な取り組みです。採用企業は適切な調査手法を適用し、正確な学歴情報を入手することで、公正な採用を実現し、信頼性の高い社会の構築に貢献することが求められます。
当社、Japan PIの採用調査は、学歴の確認の他にも、バックグラウンドチェック、レファレンスチェックなど幅広い調査項目をカバーしています。もし、何かお困りのことがありましたら、無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合せください。